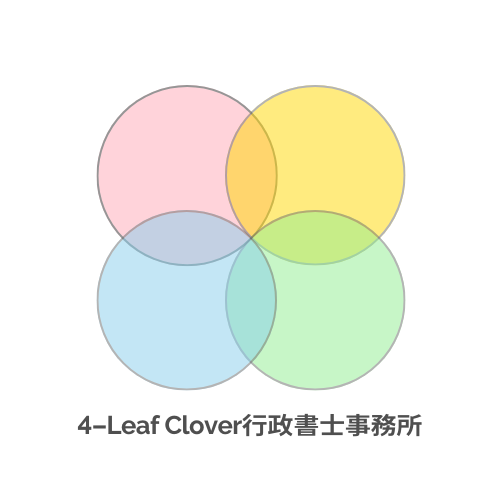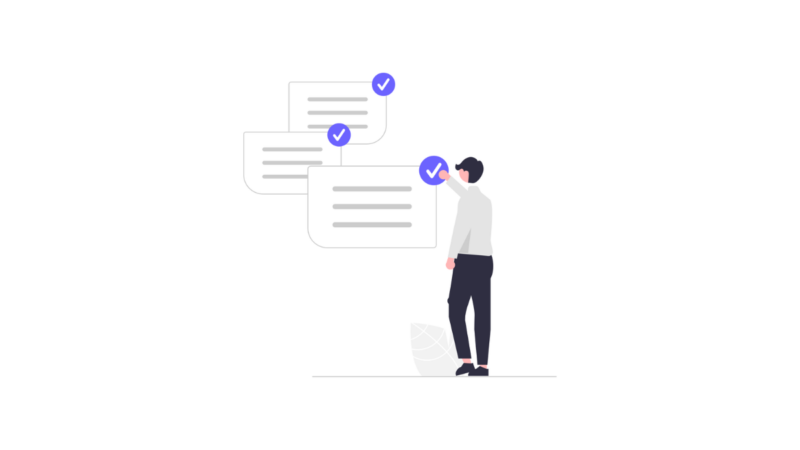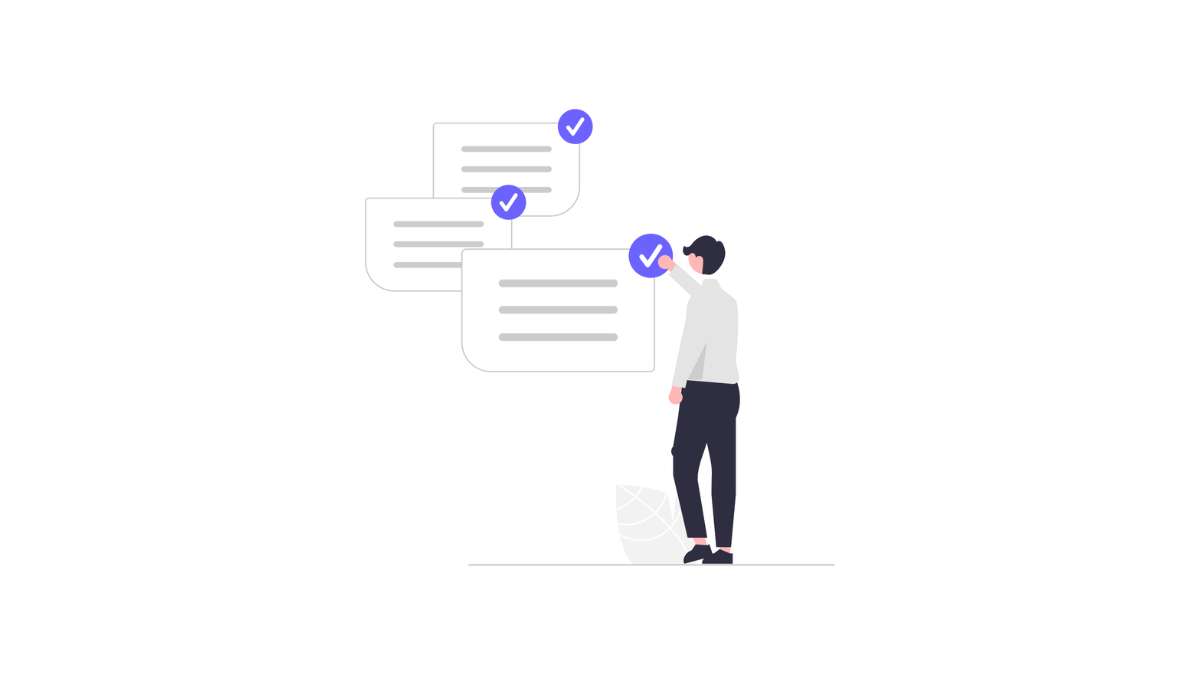
施行は2026年12月まで!民間事業者がDBS認定を取得するための「3段階ロードマップ」
目次
「2026年12月までの施行」が意味するもの:民間事業者の猶予期間はあとわずか
「日本版DBS法」(こども性暴力防止法)の施行に向けたカウントダウンが始まっています。こども家庭庁の公式見解に基づき、DBS制度は遅くとも2026年12月25日までに施行されることが確定しています。
法律上の義務がない民間事業者の皆様にとって、認定制度への参加は任意です。さらに、法律の施行までに「認定を取得しなければいけない」わけでもありません。
しかし、競合他社が認定を取得した場合を考慮し、予め何をどのように準備すべきかを知っておくに損はありません。 つまり、保護者や社会からの信頼獲得、そして事業継続のリスク管理のため、この施行までの期間を最大限に活用するための具体的な行動を行政書士の視点から、民間事業者が認定取得に向けて取るべき「3段階ロードマップ」として具体的に解説します。
【ロードマップの第1段階】
施行前(〜2026年前期まで):認定取得の「戦略的準備」
この期間は、認定取得のための新たな情報が公表されつづける期間です。
よって、新情報を常にチェックするとともに、事業者において「認定を取得する意義」を明確にしましょう。自社の内部でDBSの認定を取得する意義がある場合は、それを事業戦略として固め、リソース(認定取得の費用、人員)の確保を計画することとなります。
この戦略的準備の有無が、後々の認定手続きのスピードと成功率を大きく左右します。
認定取得の是非の最終決定と事業特性の再確認
まずは、貴社の事業が第3回で解説した「継続性」「閉鎖性」「支配性」といった、子どもと密接な接触を伴う特性を持っているか、改めて確認してください。その上で、認定取得による以下の要素を比較し、経営判断を下します。
- 認定のメリット:社会的な信頼性向上、競合他社との差別化、採用活動におけるアピール。
- 認定のコスト:申請費用、規定整備費用、情報管理体制構築費用、継続的な研修、監査時の対応コスト。
この意思決定は、その後の全ての準備の起点となります。
認定体制構築のための予算と社内リソースの確保
認定の維持には、初期費用に加え、法定研修の実施費用、機密情報を扱うためのIT環境整備費用、子どもの安全確保体制強化に向けた設備構築(防犯カメラの設置)など、継続的なコストが発生します。
特に、情報管理体制の構築や、研修プログラムの設計、さらに安全確保体制の構築(防犯カメラ)を決定した場合には、相応の予算と時間が必要です。法務・人事・ITなどの関連部署と連携し、必要な人的・物的リソース(予算)を早期に確保する計画を立ててください。
既存従業員への制度周知と理解促進(協力体制の土台作り)
DBS認定は、従業員一人ひとりの協力なしには成立しません。特に第4回で解説した戸籍電子証明書提供用識別符号の提供など、プライバシーに深く関わる手続きへの協力は不可欠です。
この段階で、制度の目的(子どもの安全)と、確認の厳格な範囲(特定性犯罪のみ)を従業員に丁寧に説明し、不必要な不安を取り除き、協力体制の土台を築いておくことが、制度導入の最大の鍵となります。
【ロードマップの第2段階】
施行直前(2026年夏〜秋):政省令・ガイドラインに基づく「体制整備」
この期間は、こども家庭庁から具体的な政省令や認定ガイドライン案が公開された後、その内容に基づいて社内規定を急速に整備する期間です。行政文書の公開後、対応を誤ると、一気に認定申請の出遅れにつながります。
特定性犯罪確認に関する社内規程の策定・修正(就業規則含む)
認定申請には、特定性犯罪歴の確認手続き、不適格者を雇用しない・配置転換するための措置、秘密保持などに関する明確な規程が必要です。
これらは、採用時の誓約書、既存従業員との合意、そして就業規則の変更という形で反映させなければなりません。就業規則の変更は労働基準監督署への届け出が必要となるため、行政手続きに精通した専門家による法令遵守チェックが必須となります。
機密性の高い情報管理体制とセキュリティポリシーの確立
DBS手続きにおいて事業者が取り扱う「戸籍電子証明書提供用識別符号」やこども家庭庁からの回答書は、機密性の極めて高い個人情報です。
これらの情報を、目的外利用しない、厳重に保管する、アクセス権限を限定するための物理的・IT的な管理体制(セキュリティポリシー)を確立しなければなりません。情報漏洩は認定の取り消しや、後の刑事罰・損害賠償請求に直結するため、この体制構築は最も慎重に進める必要があります。
法定研修義務を果たすための研修計画の策定と実施
認定事業者は、全ての従業員に対し、性暴力防止に関する研修を実施することが義務付けられます。単に研修を行うだけでなく、研修のカリキュラム、実施頻度、対象者の範囲、効果測定の方法などを記した研修計画を行政機関に提出する必要があります。認定までの限られた期間で、全従業員が受講できる具体的な年間計画を策定し、実施体制を確保してください。
【ロードマップの第3段階】
施行後:こども家庭庁への「認定申請と維持」
第1段階、第2段階の準備が整って初めて、行政手続きの本番である認定申請に移ります。認定取得後も、事業者には体制維持の義務が課せられます。
認定申請書の作成と提出、及び行政機関からの審査における対応
認定申請は、策定した各種規程やその他指定された書類などをこども家庭庁(内閣総理大臣)に提出します。
申請書類の記載内容に不備や疑義がある場合、行政機関からの質問や追加資料の提出要請がなされます。行政書士などの専門家を介することで、行政側の意図を正確に把握し、迅速かつ的確な審査対応が可能となります。
認定後の定期的な報告義務と体制維持の重要性
一度認定を受けた後も、事業者は認定基準を遵守し続ける義務を負います。
特定性犯罪の確認状況や、情報管理の体制、子どもの安全を確保していることを内閣総理大臣(こども家庭庁)に定期的に報告する義務が生じます。この報告義務を怠ったり、体制が形骸化したりすると、以下のリスクが生じます。
情報管理の不備による監査対応・認定取り消し・罰則の可能性について改めて警告
認定事業者は、こども家庭庁等による行政監査を受ける可能性があります。特に機密情報の管理体制が不適切であると判明した場合、または法令の定める義務(研修、報告など)を履行していないことが確認された場合、以下の事態に直面します。
- 行政からの監査対応や是正命令
- 認定の取り消し(事業の社会的信用の失墜)
- 罰則の適用(刑事罰や過料)
認定取得はゴールではなく、厳格なコンプライアンス体制を維持し、子どもの安全を最優先し続けることの始まりです。
まとめ:「認定準備の遅れ」は事業停止リスク。専門家とタッグを組み、計画的に進めよう
DBS制度の施行開始は、日本のこども関連事業の安全基準の1つが法的に定まり、運用が開始することを意味しています。今後、この法律で定められた基準に基づき、」公立学校での運用が定着すれば、民間事業所においても同水準の基準を求める保護者も増えていくでしょう。よって、2026年12月からこの制度を無視することができなくなることを意味しています。
この複雑な制度対応は、単なる申請書類の作成に留まりません。企業法務、人事労務、個人情報保護、そして行政機関との折衝といった多岐にわたる専門知識が必要です。
- 「認定取得の是非の決定」
- 「就業規則等の規定整備」
- 「情報管理体制の構築」
これらを短い期間で完璧にこなすには、専門家の力は不可欠です。認定準備の遅れは、万が一の事態における事業停止リスクにつながります。
施行までの期間を最大限に活用するため、行政手続きに精通した行政書士などとタッグを組み、計画的かつ確実にDBS認定へのロードマップを進めることを強くお勧めいたします。