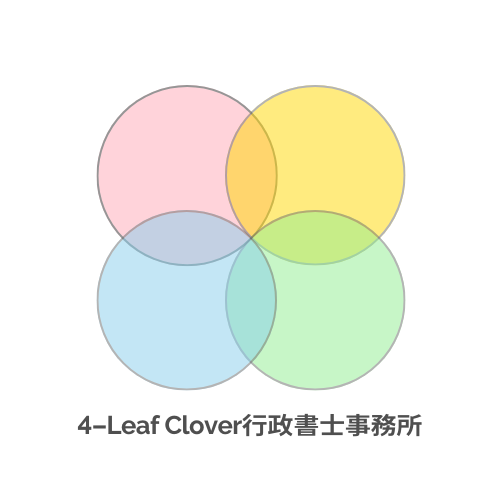就労選択支援とは?制度の概要と活用のポイント【2025年最新】
こんにちは!クローバーです。
今回は、2025年7月からスタートする『就労選択支援制度』について詳しく解説します。障害者の就労支援に関心のある方、制度の活用方法を知りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
目次
就労選択支援とは?
就労選択支援とは、支援員と障害者が能力や適性、働くうえでの課題や配慮を整理・理解し、自立した生活、将来の働き方を考えるための障害者福祉のサービスです。
背景
就労継続支援 A 型 ・ B 型の利用が始まると、 固定されてしまいやすい現状を踏まえ、障害者本人の立場に立って、障害者の自立した生活や自己実現に寄与するサービスが求められていました。
また、一般企業における障害者雇用の雇用枠の拡大など障害者が働く場は広がる一方で、未だ障害者への十分な支援がないために働くことができない、障害者が仕事を続けるのが難しい現実があり、障害者雇用に関する様々な検討がなされています。
そんな中、障害者総合支援法が改正され、2025年7月から就労選択支援が創設されました。
就労選択支援の目的
就労選択支援は、 支援員と障害者が協同で能力や適性を客観的に評価するとともに、 本人の強みや課題を明らかにし、 就労に当たって必要な支援や配慮を整理します。
具体的には就労アセスメントの方法を活用し、 本人への情報提供、 作業場面を活用した状況把握、 多機関連携によるケース会議、 アセスメント結果の作成を実施します。
そして、 その結果を本人にフィードバックして、 本人と一緒に将来の働き方などを考え、 必要に 応じて事業者等との連絡調整を実施するものです。
制度の枠組み
就労選択支援をサービスとして受けられる方やサービスの流れは次のとおりです。
対象者(どのような人が利用できるか)
支援の対象者は次の方たちです。

支援の流れ(申し込みから利用開始まで)
就労選択支援は、さまざまな支援機関などから利用の相談を受けることから始まります。本人の就労に関する状況把握を行い、 その結果から的確な進路選択につながるよう情報提供します。 提供された情報に加えて、 家族や関係機関などの意見も必要に応じて加え、 本人が就労に関する進路の決定を支援することが、 就労選択支援の基本プロセスです。
また、就労選択支援事業所は、指定特定相談支援事業者や就労系障害福祉サービス事業所、市区町村、ハローワークなどの連携、連絡調整を行います。さらに、地域の雇用事情も踏まえた情報提供も求められるため、地域の事情に精通することも事業者として求められる要素となります。

就労選択支援の事業者の要件
実施主体となりうるもの
実施主体となる事業者は前述の図に記載の通り、以下の4つのサービスを実施しなければなりません。
- サービスとして実施すべき内容
- 作業場面を活用したアセスメント実施
短期間の生産活動等を通じて、 就労に関する適性等の評価や意向等整理します。 - 多機関連携によるケース会議
アセスメント結果の作成に当たって、 利用者および関係機関等を招集して多機関連携によるケース会議を開催します。 - アセスメントシートの作成
アセスメント結果を作成し、利用者等へ情報提供します。 - 事業者との連絡調整
利用者への適切な支援に向け、必要に応じて事業所など関係機関との連絡調整を行うことが規定されています
- 作業場面を活用したアセスメント実施
- 定員 10 人以上
- 職員配置 管理者、 就労選択支援員
- 従事者の人員配置・要件
- 就労選択支援員の人員配置 15 : 1 以上
- 就労選択支援は短期間のサービスであることから、 個別支援計画の作成は不要、 サービス管理責任者の配置は求めないこととなっています。
- 就労選択支援員の要件 就労選択支援員養成研修を修了していること。
- その他の留意事項
- 利用者に対して、直接支援を行った場合が報酬算定の対象となります。利用者が同席する多機関連携によるケース会議や企業訪問は算定対象となりますが、関係機関との連絡調整等のみ行うなど、 利用者の参加を伴わない場合は算定対象になりません。
- 就労選択支援は、 本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法 を活用して、本人の希望、 就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです。 本人との協同による意思決定を支援するサービスであり、 就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではありません。
例えば、アセスメントシートに、想定される事業所名を記載する場合などが考えられますが、それはあくまで参考情報に過ぎず、就労選択支援事業者が利用するサービスのあっせんを行うものではないということです。 - また、就労選択支援サービスから、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型に繋げるにあたり、正当な理由がなく特定の事業者に集中している場合は、特定事業所集中減算が適用されます。(よって、算定のための書類の提出や正当な理由を証明する書類の提出が必要となります。)
事例
モデル事業の事例については、実施マニュアルに記載があります。細かな点についてご興味のある方は、33ページからの資料をご参照ください。
厚生労働省 「就労選択支援実施マニュアル」https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001480295.pdf
就労選択支援は、多様性社会の実現に大きく寄与するサービスです。しかし、これから実施する制度のため、同一市区町村内に就労選択支援の事業者があるか否かによって、実施主体の要件に地域格差が発生すると予想されます。そのため事業開始の判断が難しい点もありますが、人口減少社会の日本においては、障害者の能力を生かす場、発揮できる場が増えると思います。障害者の就労機会を広げるために、事業者としての取り組みが重要になります。事業者の方は、導入に向けた準備を進めることで、障害者の雇用機会拡大に貢献できます。
次回は、就労選択支援に欠かせない支援員に関してお届けします。明日の記事もお楽しみに🍀