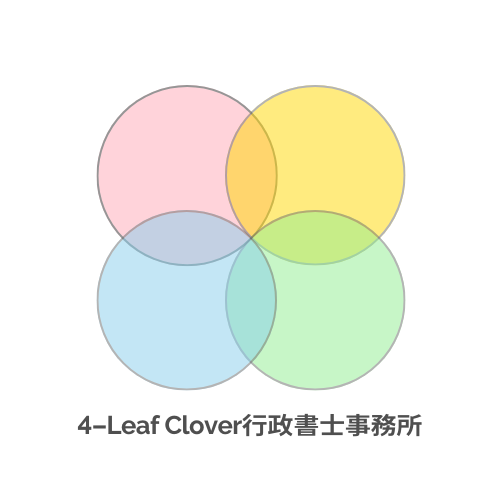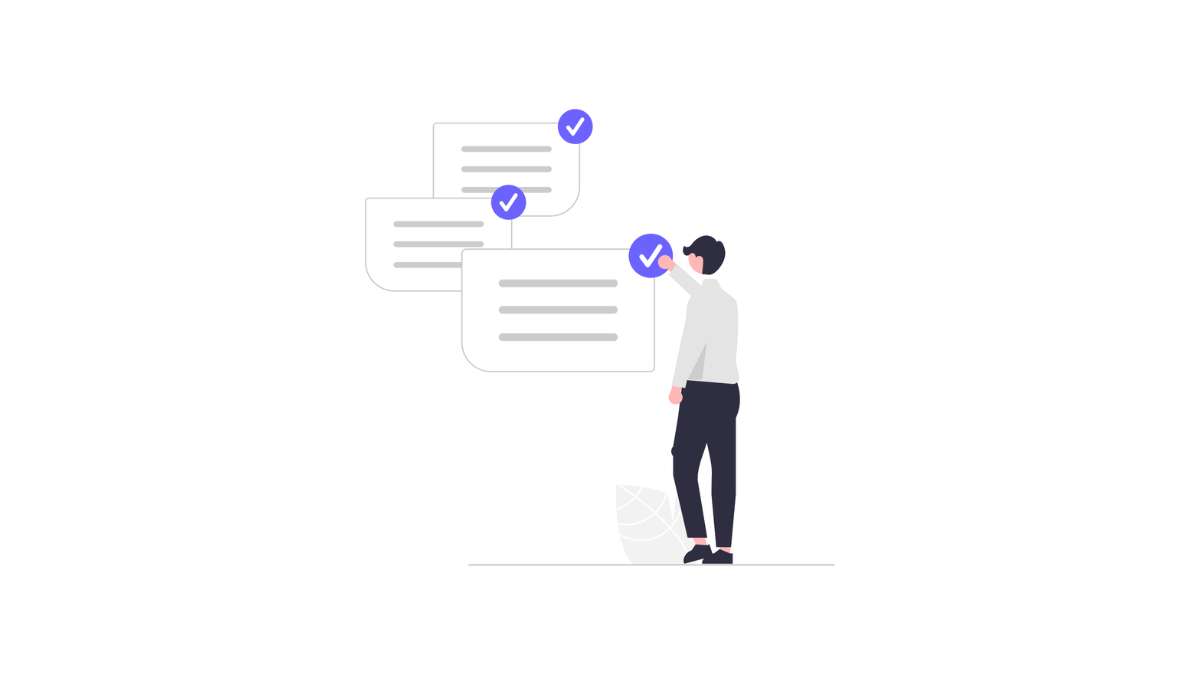
障害福祉サービスの適正化へ—運営指導と監査の強化
こんにちは。クローバーです。
近年、障害福祉分野において運営指導・監査の強化が求められています。今日から3回にわたって、障害福祉分野の運営指導・監査の強化についてお届けします。
今回は、障害福祉分野における運営指導・監査の強化に関する見直しに関するポイントに焦点を当てます。
運営指導・監査の強化に至った背景
株式会社恵の運営する障害者グループホームにおいて食材費の過大徴収が組織的にあったことが明らかとなり、指定取消処分が行われ、多くの利用者に影響が出ました。
また、近年は事業所数が急増しており、障害のある方々が安心して質の確保されたサービスを利用できるよう、運営指導・監査の強化する必要性が出てきました。
課題
- 運営指導の実施率の低さ
都道府県等が事業者に対する運営指導に関する課題の1つとして、指導の実施率が低いことがあげられます。指針においては、3年に1回の運営指導の実施を求めていますが、全国平均の実施率は16.5%となっています。 - 障害福祉分野の運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方や例がない
障害福祉関係指導監督職員の研修において、介護保険分野と同様に、①公益侵害の程度、②故意性の有無、③反復継続性の有無、④組織性・悪質性の有無 等を踏まえて総合的に判断するよう示しているものの、介護保険分野のように標準化された運営指導・監査マニュアルや処分基準はありません。
自治体からも処分理由や内容に不合理な状況が生じないよう、全国標準の考え方を示してほしいという指摘があがっていました。 - 大規模な運営法人に対する業務管理体制の検査が十分に行われていない
指定事業所等が2つ以上の都道府県にある障害福祉サービス事業所は国が所管していますが、これらすべての事業所に対して業務管理体制の検査が徹底できていませんでした。
また、実地検査対象外となった事業者は書面検査を受けることとなるのですが、書面検査が実施されなかったり、方法も聞き取りとなっており、定めた方法によった検査となっていませんでした。 - 事業者向けの研修が効果的ではない
国所管の障害福祉サービス事業所に対して指導監査に関する研修を実施しているものの、参加率が低い(令和5年36.4%)こと、また研修内容に関して参加した事業者から、研修内容が画一的で取組事例の情報ないとの声もあがっており、研修の運営に関する課題も浮かび上がりました。
事業者が対応すべきポイント
- 法令等に従った運営となっているか現状を把握する
- 指導検査項目は、組織運営、提供するサービス、会計と3領域にわたり、内容も日常の業務レベルの細かい点に着目しています。そのため、日ごろの業務運営がルールに従ったものなのか状況を把握することが必要となります。今までは、事業所開設後、新型コロナの流行等で指導を受けず数年経った事業所も多数かと思われますが、今後は運営指導の通知が来ることは否定できません。そのため、今のうちから少しずつ運営状況を確認・整理・見直しをしましょう。
- また、社会保障審議会において、令和7年度中に障害福祉分野の運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方の例を作成することが公表されていますので、最新の情報も注視する必要があります。
- 事業者向けの研修に必ず参加する
- 今後、事業所向けの研修は、オンライン講義だけなく実践報告を取り入れ、受講したかを確認する仕組みを取り入れる予定です。また、研修未受講の法人は、業務管理体制の一般検査の優先順位をあげることを検討している模様です。
- 研修を受けたから運営指導等の対象とならないわけではありませんが、少なくとも研修の案内・通知がきたら必ず受講すれば、指導の時期を早めることに繋がらないと予想されます。よって、研修の参加も地道ですが、重要な取り組みと捉えることができます。
障害福祉分野の運営指導・監査の強化について、今日の記事では概要をお伝えしました。次回、次々回はより具体的な内容に踏み込んで
- 指導と監査の違い
- 現行の指導の流れ
をお届けします。
具体的な指導の流れを詳しく解説するので、ぜひ明日もご覧ください。