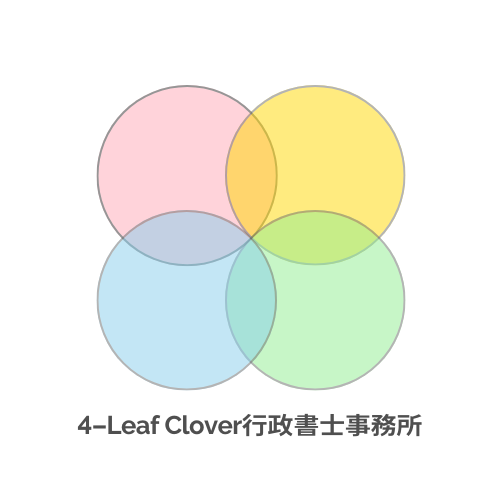【基本のき】日本版DBSとは?行政書士が解説する「子どもを守る責務」の本質と制度の全体像
目次
はじめに:日本版DBS導入の背景:なぜ今、この制度が必要なのか(約350字)
近年、子どもたちが関わる習い事や教育の場で、指導者による痛ましい性暴力事件が相次いで発生しています。社会全体で「子どもを性被害から守る」ための対策は喫緊の課題となり、特に、指導者として子どもたちと密接に関わる事業者を対象とした「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」制度の導入が決定しました。
この制度は、英国などで先行導入されている仕組みを参考に、「子どもと接する仕事に就く者の性犯罪歴の有無を確認する」ことを可能にするものです。しかし、単に「前科をチェックする制度」という表面的な理解だけでは、その本質を見誤ります。
行政書士である私の見解として、この制度を「子どもの安全を守るための環境整備を法的に位置づけたもの」として捉えることが重要だと考えます。今回はシリーズ第1回目として、DBS制度の根本的な概要と、事業者が負うべき「責務」について、基本の「き」から徹底的に解説します。
DBSの核心:「子どもを性暴力から守る環境づくり」という仕組みの全体像
日本版DBS制度は、子どもが心身ともに健全に発達できるよう、学校や保育所、学習塾など子どもに教育・保育を提供する事業者に対し、性暴力を防ぐための包括的な取り組みを求める制度です。
この制度で求められる「子どもの安全を守る環境づくり」には、単なる犯罪歴の確認に留まらない、多角的な取り組みが含まれます。具体的な取り組みは以下の通りです。

この制度において「特定性犯罪歴の確認」は、最も注目される特徴ではありますが、それはあくまでも、前述の「子どもへの性暴力防止のための環境整備」という包括的な責務を果たすための重要な手段の一つでしかありません。
したがって、学校や塾、習い事を提供する事業者の皆様にとっては、DBSの導入は、組織全体の安全基準を向上させ、リスク管理とコンプライアンスを強化することに直結するものです。この包括的な責務を負う点が、この法律の重要な特徴と言えます。
DBSの仕組みは、事業者が自由に個人の前科を調査するものではありません。これは公的機関(こども家庭庁や法務省など)が、従業員本人の同意に基づき性犯罪歴を確認し、その結果を「特定性犯罪歴の有無」という形で「犯罪事実確認書」として事業者に通知する、極めてプライバシーに配慮された仕組みを採用しています。この点も、従業員の方々に正確に伝えるべき重要な基本情報です。
事業者に求められる「責務」とは?
DBS制度が事業者にもたらす影響は、法律で定められた事業の性質に応じて「義務化の対象となる事業者」と「認定(任意)を取得する事業者」という二つの側面から理解できます。
- 義務化の対象となる事業者
まず、法律でこの制度の実施が義務づけられるのは、学校や保育所、児童養護施設などの「公的機関等」です。
これらの事業者は、法律に基づき、「子どもが安全に過ごせる環境づくり」のための防止措置や職員を採用・配置する際に性犯罪歴の確認を「必ず行わなければなりません」。これは、公的サービスを提供する上での当然の社会的責任として位置づけられます。 - 認定を任意で取得する事業者
一方、多くの塾、習い事教室、スポーツクラブ、ベビーシッターサービスなどの民間事業者は、「認定事業者」の制度を利用することができます。
国(こども家庭庁等)から認定を受けた事業者は、子どもへの性暴力防止に関する高い安全基準を満たしている証を得ることができます。認定事業者となった場合、対象となる職種の従業員に対し、DBSによる特定性犯罪歴の確認や性犯罪の防止など「子どもが安全に過ごせる環境づくり」の取り組みを実施する責務が発生します。
認定事業者となるか否かは事業所の判断に委ねられるため、義務化されている公立学校等と異なり「任意」です。しかし、この「任意」は「対応しなくても良い」という意味ではないことに、事業者は細心の注意を払う必要があります。
「任意」でも認定取得を意識すべき理由
事業の信頼性と競争力の維持
保護者や社会は、民間事業者に対しても、DBSの義務化されている公立学校と同レベルの安全基準を求めてくる可能性があります。また、認定を取得しないことは、競合他社との比較において信頼性低下に直結するリスクとなります。
つまり、今後はサービスの質に加え、安全な環境かどうかが選定基準として重要視されるため、認定は競争力の維持に不可欠な要素となりうるため検討や認定取得に向けた準備をしていく必要がでてくるでしょう。
リスク管理体制の確立
DBS認定を受けることは、性暴力防止への高い意識と、安全管理体制が確立されている証となります。行政書士である私の視点から見ても、これは事業継続における必須のリスクヘッジとなると考えます。
したがって、民間事業者であっても、法律の施行後は「認定を受けること」を実質的な責務として検討し、施行に向けた計画的な準備を進める必要があります。
事業者が知っておくべき「基本のき」3つのポイント
DBS制度導入に向け、事業者がまず押さえるべき基本情報を3つのポイントにまとめます。
【ポイント1】確認対象は「特定性犯罪」のみ:全前科が調査対象ではない
DBSで確認されるのは、刑法で定める「特定性犯罪」に限られます。
これは、制度の目的が「子どもへの性暴力の防止」という極めて限定的なものであるためです。飲酒運転や窃盗などの性犯罪以外の前科・犯罪歴は確認の対象外です。
さらに、確認期間にも厳格な制限が設けられています。
- 拘禁刑:20年間(執行猶予の場合は10年間)
- 罰金:10年間
このように、対象となる犯罪歴は限定的かつ期間も定められているため、「すべての前科をすべて洗い出す」といった誤解や、従業員の過度な不安を払拭するためにも、制度を正確に理解しておく必要があります。
【ポイント2】事業者が直接「前科の有無」を知るわけではない
前述の通り、DBSの仕組みは、事業者が直接かつ勝手に従業員の前科情報というセンシティブな個人情報に触れることを避ける設計になっています。
- 従業員から戸籍に関する情報を提供してもらい、それをもとに事業所から公的機関に対し性犯罪歴の照会を申請します。これは、従業員の協力と同意を得て初めて特定性犯罪歴を照会できることを意味します。
- 公的機関は、照会結果を「特定性犯罪歴なし」といった限定的な情報が記載された「犯罪事実確認書」の発行を予定しています。
- 事業者は、この証明書を確認することで、採用・配置の可否を判断します。
事業者が知ることができるのは、あくまで子どもの安全を確保するために必要な「要件を従業員が満たしているか否か」という判断に必要な最低限の情報のみです。また、とてもセンシティブな情報のため、プライバシー保護と事業活動の円滑化の両立を事業者に求めています。
【ポイント3】施行は「2026年12月まで」:認定取得に向けた「計画的な準備」を推奨する理由
日本版DBSの法案は成立し、「2026年12月までの施行」が期限として設定されています。
民間事業者の「認定」は任意であるため、施行後すぐに取得しなくても法令違反となるわけではありません。
しかし、行政書士として、施行を待たずにできるところから準備を進めることを推奨します。
その理由は、事業の差別化と円滑な経営に直結するからです。
事業の信頼性・差別化の確立
施行開始前に準備を終え、早期に認定を取得することで、保護者や利用者に「安全対策に積極的な事業者」として、他社との明確な差別化を図ることができます。これは顧客獲得において大きなアドバンテージです。
実務対応のコスト最適化
「認定事業者」となるためには、社内規定(就業規則等)の整備や、従業員への研修、行政への申請、派遣会社や業務委託会社との契約見直し、情報管理体制の強化など、煩雑な実務対応が必要です。早めに少しずつ着手することで、外部の専門家から高額な依頼コストを求められたり、実務的コストや負担を分散・最適化します。
既存従業員への対応準備
制度開始後、既存の従業員への確認手続きには経過措置期間が設けられます。この期間内に全従業員の対応を完了させるためには、事前の周知や同意取得など、人事・労務の観点から計画的な準備が不可欠です。
施行までの期間を逆算し、計画的に準備を進めることが、事業の成長と信頼性確保につながります。
まとめ:DBS導入は事業の信頼性を高めるチャンス
日本版DBS制度は、単なる「手続き」や「規制」ではありません。それは、子どもたちに「安全・安心」という最も重要な価値を提供する、現代の事業者にとっての必須の責務となるでしょう。
特に民間事業者が「認定事業者」となることは、保護者や地域社会からの揺るぎない信頼を勝ち取ることにつながります。この制度導入を、事業のリスク管理体制と社会的な信頼性を高める絶好の機会として捉えましょう。
当事務所では、DBS認定に向けた社内規定の整備、行政手続きのサポートなど、事業主様がスムーズに制度に対応するための万全のサポート体制を整えています。不安や疑問点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。