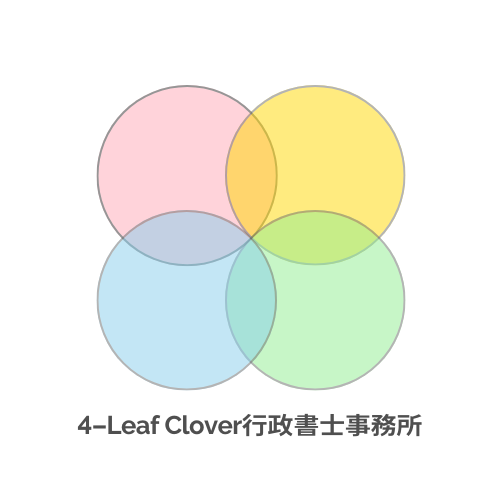日本版DBS制度:塾・習い事は「義務」?「認定」で信頼を可視化する戦略と適用論点【行政書士解説】
目次
「義務化」のニュース、うちの塾も対象ですか?
学習塾や音楽教室、スポーツクラブなど、子どもと日常的に関わる事業を運営されている皆さまへ。2024年6月に「こども性暴力防止法」(日本版DBS法)が成立し、「性犯罪歴の確認(DBS)が義務化される」というニュースを目にして、不安を感じていませんか?
「うちのような民間の小さな教室も、煩雑な手続きを義務付けられるのか」「既存の先生たちも全員、犯罪歴を調べられるのか」といった疑問や懸念を多くお聞きします。
しかし、ご安心ください。結論から申し上げると、一般的な塾や習い事事業者は、法律上「義務化」の対象ではありません。
当記事では、こども家庭庁の「中間とりまとめ」を基に、日本版DBS制度における「義務」と「任意(認定)」の明確な線引きを解説します。そして、貴社が取るべき最善の道筋、すなわち「任意」である認定制度を取得する経営的なメリットを行政書士の視点からお伝えします。
DBSが「義務」となるのはどこか?「公的機関等」の定義
法律上の「義務化」対象となる事業者
「こども性暴力防止法」に基づき、DBS制度の運用が法律で直接義務付けられるのは、公的な責任の下で教育・保育を提供する以下の事業者です。
- 学校設置者:幼稚園、小学校、中学校、高等学校など
- 認定こども園、保育所、児童養護施設などの児童福祉施設の設置者
これらの事業者は、制度施行後、教員や保育従事者を雇用・配置する際に、DBS制度における特定性犯罪の確認や子どもの安全確保措置の実施が義務となります。
なぜ塾・習い事は義務ではないのか?
現行の法律構造において、一般的な学習塾や民間のスポーツ教室などは、上記のような公的な教育・福祉の枠組みとは別に位置づけられています。
そのため、現在の制度設計では、「民間事業者」に対してDBS制度の運用が法律で義務付けられていません。義務となるのは、あくまで事業者が「認定事業者」となった場合です。
これが、皆さまの事業に対する法的な立ち位置の「基本のき」です。
ただし、義務でないからといって「何もしなくて良い」わけではありません。むしろ、「任意で認定を取得する」という戦略的な選択が、今後の事業運営において極めて重要になってきます。つまり、認定事業者としての責務と認定を取得することによる信用とのバランスを考え、今後の経営戦略を練る必要があります。
民間事業者の本命:「認定制度(任意)」のメリットと要件
「認定制度」とは:信頼を可視化するマーク
義務化の対象外である民間事業者は、国が定める「認定制度」に定められた条件を満たすと認定を取得することができます。
認定を受けた事業者は、国から「子どもを性暴力から守る体制を整えている」というお墨付き、すなわち「認定マーク」の掲示が可能になる見込みです。
これは、単なる手続きではなく、保護者や社会に対する「安心宣言」です。少子化が進み、保護者の教育サービスに対する選定基準が厳しくなる中、「安心・安全」を可視化できるこの認定は、強力なブランディングと集客の武器となります。
認定を受けるためにクリアすべき「安全確保措置」
認定を受けるためには、単に「特定性犯罪歴の照会手続きができる体制があればいい」といった簡単なものではありません。
犯罪歴は極めてセンシティブな情報のため、それを厳重に情報を管理するIT環境と情報規程などの体制整備はもちろんの事、何より日ごろから包括的な「子どもの安全確保措置」を講じることができることが要件となります。
未然防止体制の整備
従事者(講師、スタッフ)に対し、性暴力防止に関する定期的な研修を実施すること。
子どもの性暴力に関する相談窓口を設置し、日ごろから性暴力を未然に防ぐための環境を整えること。
性暴力発生時の子どもの保護・支援体制の確立
性暴力が発生した場合、またはそのおそれがある場合の初動対応、事実確認調査、および被害を受けた子どもへの適切な保護・支援を行う体制を明確に構築すること。
社内体制の整備(必要な規程等の整備と環境構築)
服務規律(就業規則)に懲戒に関する規程を修正したり、情報管理規程を明確化したマニュアルなどの各種規程を整備すること。これらの規程に基づき、DBS確認記録の適正な管理や、不審な行動を察知できる環境(設備)の構築など、組織的な体制を整えること。
これらの措置は、法令遵守と実務運用が密接に関わるため、体制構築の設計と文書化が非常に重要となります。特に小規模な塾や教室では、これらの規程整備を本業の傍らで完璧に行い、継続的に維持していくことは困難です。 複雑な法制度に基づいた規程の作成や、行政手続きを伴う体制の構築は、法務・行政手続きの専門家に依頼することで、確実に、かつ効率的に進めることが可能です。
実務の核心:DBS制度運用で「混乱のもと」となる論点
ここでは、特に塾・習い事事業者の皆さまが注目すべき、主要な論点について解説します。
論点①
子どもに対して技芸や知識の教授する事業であり、「支配性・継続的・閉鎖性のある事業」かどうかの判断
民間事業者を認定の対象とするか否かの基準として、業務の性質が以下の要件を満たす場合に焦点を当てるべきとされています。
- 支配性: 子どもを指導するなどし、非対称の力関係がある中で、支配的・優越的立場に立つこと。
- 継続性: 時間単位のものを含めて子どもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと。
- 閉鎖性: 事業者が主体的に場所や区画を選択するといった性暴力等が露見しづらい環境で指導を行うこと。
具体例
- 個別指導塾のマンツーマン指導や、長期にわたるスポーツのコーチングは、「支配性」「継続性」「閉鎖性」を満たしやすく、認定制度に参加する意義が非常に高いと考えられます。
論点②
従事者の範囲(アルバイト・業務委託)
特定性犯罪歴の調査の対象となる「従事者」の範囲について、雇用形態を問わないという方向性が示されています。つまり、パート社員、派遣社員、業務委託契約者などの契約の種別ではなく、「子どもと接する仕事かどうか」によって犯罪歴の調査の要否を判断することとなります。
- パート、アルバイト講師: 雇用契約の有無や勤務時間に関わらず、子どもと継続的に接触する業務に従事する場合は確認の対象となります。
- 業務委託(フリーランス)講師: 雇用契約がなくとも、事業者の責任の下で指導を行っている場合、認定制度に参加する事業者はこれらの外部講師に対しても確認手続きを行うか、それに準じる措置を講じる必要が出てきます。
行政書士の視点
業務委託契約書や、派遣元の会社との契約や派遣社員の派遣契約に特定性犯罪の調査に関する個人情報の取扱いについて協力義務を盛り込むなど、契約書・規約の見直しが必須となります。
論点③
特定性犯罪の犯罪歴の確認の期間(既存従事者)
義務化の対象である学校等では、制度施行後3年以内に現職者全員の確認を行う方向ですが、認定を受けた民間事業者については、「認定から1年以内に現職者全員の確認を完了させる」ことが論点として挙げられています。
「認定を受ける」という意思決定をした瞬間から、既存従業員に対する説明や特定性犯罪の調査に関する同意確認などの手続きのカウントダウンが始まります。このため、認定を受ける時期や認定取得して1年が経過する日から逆算し、人事部門などと連携した周到な準備計画が必要となります。
まとめ:過度な不安は不要。大切なのは「認定」に向けた計画的な準備
貴社の事業が法律上の「義務」を課されないものの、「認定制度」は今後の経営において「子どもたちの安全」と「事業の信頼性」を両立させるための最重要戦略です。
今すぐやるべきこと
- 自社の事業の確認
「継続的・反復的・閉鎖性な指導」であるか、特にマンツーマン指導などの形態がないかを確認する。 - 認定の取得の是非や取得時期をいつにするのかを決断
認定制度の要件(体制整備、規程整備、環境構築)を前向きな投資として捉える。 - 専門家への相談
煩雑な規程整備や行政への申請手続きは、行政書士の専門分野です。さらに、既存従業員への対応というデリケートな人事問題は、労働問題に精通した社労士などの専門家との連携も可能です。スピーディかつ正確に準備を進めたい方は専門家への相談も前向きにご検討ください。
過度な不安に駆られるのではなく、この制度導入を業界全体の信頼度向上のチャンスと捉え、計画的な準備を始めましょう。もし、進め方や手続きに不安な方は、行政書士と一緒に準備を進めることをお勧めします。
【お問い合わせください】
当事務所では、貴社の事業形態に合わせたDBS認定制度の導入支援、必要な規程・マニュアルの作成、そして行政への申請サポートを一括して承っております。まずは無料相談をご利用ください。